 文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪 大臣塚古墳 骨と剣が副葬品、百合若と伝わる武人が眠る
大分市元町にある大臣塚は、江戸時代初期の台風により中から白骨や刀剣などの副葬品が見つかったが当時の府内藩主である日根野吉明が埋め戻し、石碑を立てて丁寧に供養もしたという。また、大分の百合若伝説に関わる重要な場所でもある。
 文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪  文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪  文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪  魚名表現(方言や漢字)
魚名表現(方言や漢字) 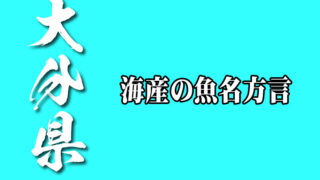 魚名表現(方言や漢字)
魚名表現(方言や漢字) 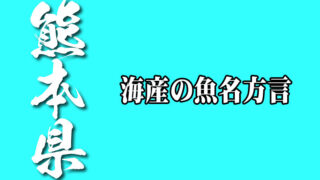 魚名表現(方言や漢字)
魚名表現(方言や漢字)  魚名表現(方言や漢字)
魚名表現(方言や漢字)  魚名表現(方言や漢字)
魚名表現(方言や漢字) 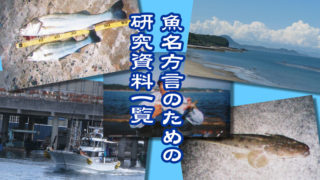 魚名表現(方言や漢字)
魚名表現(方言や漢字)  文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪