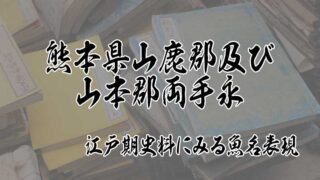 魚類史料・伝承
魚類史料・伝承 肥後国山鹿郡と山本郡の江戸期史料から菊池川中流域の魚名を見る
『山鹿郡山鹿中村両手永名品』と『山本郡正院手永土産』は、肥後細川藩が江戸幕府に提出した『肥後国之内熊本領産物帳』を作成する際の基礎資料となったものの一部とされる。ここでは熊本県北の魚種及び魚名方言調査の一環として読解してみた。
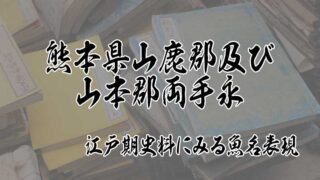 魚類史料・伝承
魚類史料・伝承 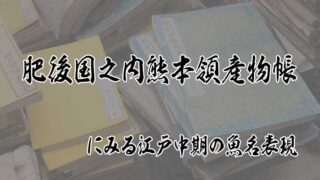 魚類史料・伝承
魚類史料・伝承  エノハの渓へ(旧釣行記)
エノハの渓へ(旧釣行記)  エノハの渓へ(旧釣行記)
エノハの渓へ(旧釣行記)  エノハの渓へ(旧釣行記)
エノハの渓へ(旧釣行記)  エノハの渓へ(旧釣行記)
エノハの渓へ(旧釣行記) 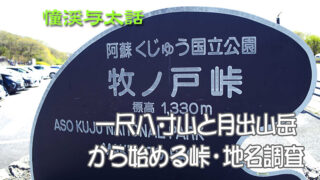 憧渓の雑記
憧渓の雑記  文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪  文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪  文化財・史跡探訪
文化財・史跡探訪